![]()
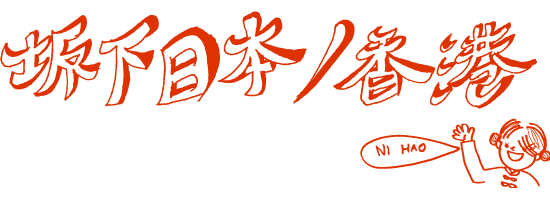
第117回「あらためて始めました」
我ニーハオ、ニホンコンです。
先週お話した臭い缶詰、シュールストロミングは
「楽しく、美味しく(?)食べてくれそうな友人」
に狙いを定め、突撃ではありませんが、
「あげるよ!」メールを送りつけ、ビビられながらも
快く(?)受け取ってもらえることができました。
これで我が家の毒ガス爆弾が減りました(ウソウソ)
2名には是非「食べたよ!レポート」をしてもらう
ことになりましたので、ニホンコンのものとあわせて
楽しみに待っていてください。
さて、この夏。
ニホンコンはひとつ再開したことがあります。
それは「中国語の勉強」です。
留学時には割と真面目に勉強していたので
ペラペラとまではいきませんが「ペラ」
くらいまで到達したと自負していたものの、
帰国後は旅行程度にしか使っていなかったので
だいぶ衰えてしまいました。
帰国後5年たってようやく重たい腰を
あげて勉強を再開。
動機は10年来の香港人友人と
先日久しぶりに電話で話す機会があり、
一言「坂下(バンシャー)、北京語ヘタクソになったねー!」
と言われたのがショックで。
その友人とは、外国語の会話でも
とても理解することができ、
香港で一番仲良しの現地の友だちだったのだが、
こないだの電話では時折何を言ってるのか
聞き取れないこともしばし。
こ、これはイカン、と我が身の末期症状を
目の当たりにしたニホンコン。
速攻手を打たないと中国大陸で土ぼこりにまみれ、
人民と喧嘩し、死にそうになったり
死なれそうになったりした
あの時間が全くもって無駄になってしまう!
しかし。
高いお金を払って中国語教室に行くのなんて
まっぴらごめんなのと、中国人の友だちを
新たに作るとしても、恋愛に発展させる
気合いじゃないと語学なんて伸びないし。
考えたニホンコン。
ここは留学時代でもよく使っていた「相互学習」作戦に。
相互学習とは、英語圏ではランゲージエクスチェンジといいます。
日本語を勉強したい中国人と、中国人を勉強したい日本人が
集まってそれぞれ勉強を教え合うというもの。
お互いを「学友」と呼び合い、共に勉学に励むという
ホントの意味で「学友」として過ごすものです。
北京での相互学習はというと。
相手は中文科(日本で言う国文科)の学生で
将来は国語の先生を目指しているという女の子。
私の中国語の質問に、ものすごく丁寧かつ分かりやすく
教えてくれたものでした。
かくいうニホンコンの日本語なんて知れてるけれど
ここは幸いにして彼女の第二外国語の日本語がヘタクソすぎて
文法云々まで行かなかったのがよかった。
毎回「新しい単語を覚えました」といいつつ
頭を指差し「おーむーつっ!」というのだけれど、
ニホンコンにさえ、それが「おつむ」が言いたいのが
分かるので「ソレハ、マチガイデス」と指摘する程度。
殆どニホンコンの専属家庭教師状態で
不公平きわまりない学習状態でした。
今回は友人のつてで、去年国営新聞社に勤める
ダンナさんと一緒に日本にやってきた「ヤンさん」
という女性を紹介してもらいました。
彼女も北京出身ということで、お互い北京話で
毎回盛り上がり、少しずつ感覚が戻ってこようと
しております。
語学は「聞く、話す、読む、書く」の
順に覚えていくといいます。
(日本の英語教育は「読む、書く」から
始める変わった学習形態だけど)
ニホンコンは最難関の「書く」というところに
身をおくことで、そこで力を付けたいと
思い、敢えて毎回作文を書くことを自分に課す。
それが、もうひどいのなんのって。
毎回ヤンさんは苦ーい顔をしながら
どんどん赤で訂正していく。
「言いたい事は分かるけど、ねえ・・・」と
言いながら最後には殆ど別の文章が仕上がっている。
それを毎回家に帰ってまた書き直す。
こんな作業の繰り返しです。
ただ、頭の中でキレイにしまわれていたものが
少しずつ引き出されて行くのが分かり、面白い。
これから忙しくなっても、できるだけ努力して
続けられるだけ続けようと思っています。
もうヘタクソなんて言わせん!と思いつつ
私を笑った友人に「中国語勉強始めたからね!」と
伝えようとメールを開き、ふと思い出したことが。
香港は97年までイギリスの植民地ということもあり
中学からの教科書が全て英語。先生が中国語を話しながら
英語の問題を解いていく、という教育システム。
そして社会に出てからもボスが外国人というところが
多いため、殆どの香港人が「話し言葉は中国語」
そして
「書き言葉は『英語』」なのである。
く、くそー。
ディアー マイ フレンド
アイ スタート トゥ スタディー チャイニーズ アゲイン
いずれの言語においても、香港人の友人には
到底かなわない、島国育ちのニホンコン。
8月23日 坂下日本/香港
| Kaori Sakashita Presents [ サカシタニホンコン ] All rights reserved by Kaori Sakashita & SAKRA 2005 |