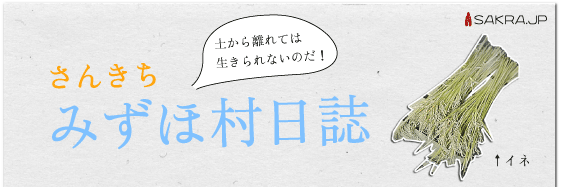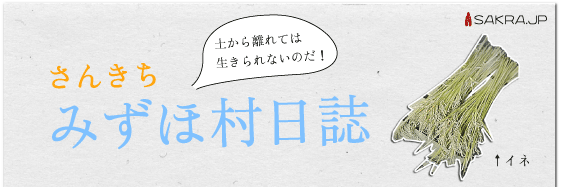〜第2回〜
はじまりはじまり編2
こんにちは。
さんきちです。
さて、みずほ村日誌2回目。
バンバン進めて行くぞ。
まずは、そもそもの、このプロジェクトのはじまりについて。
なぜ、どうして、こういうことがはじまったのか・・・といいますと、
それは、あるホテルの、生ごみ問題からはじまります。
富士吉田に、「ホテル鐘山苑」という高級日本旅館があります。
サイトはこちら
そこには、年間、宿泊で20万人、食事で10万人、
合計約30万人の利用客がいて、
毎日おいしい料理がたくさん出され、
その分、料理した際に出る大量の生ごみがでるのです。
よい食材を使っているからさ、
生ごみっつっても、かなり贅沢なもんでできてるんだけど、
その毎日でる大量の生ごみを、
どうにか有効に使う方法はないかなあと考えた結果、
どーんと決心をして、
それを、自分のところで液肥(液体の肥料)にしてしまう
機械を購入したのでした。
その液肥(1ヶ月1トンもできるらしい)を、
富士吉田の地元の農家の人々に提供し、
そうやって作ってもらった農作物を、
ホテルの朝市で売ったり、またゆくゆくは、
ホテルでお出しする料理に使っていこう
と考えたのです。
機械は高かったけど、
毎日の生ごみを無駄にしないでリサイクルでき、
それを使って、富士吉田でおいしい安全な有機作物が採れ、
ホテルも地域の食材をつかっておいしい料理が出せる。
・・・ようになったらいいなあ。
そういうホテルになりたいなあ。
まあ、まずは、とにかく、この液肥で、地域を活性化していこう。
こういう取り組みをしている地域だということをみんなに知ってもらおう。
地域の活性化がこのホテルの活性化につながるのだ。
といったような考えでもって、
ホテル鐘山苑は機械を購入したのでした。
で、その話を、富士吉田で、もともと有機農法でお米作りをしていて、
全国米コンクールで2000年から4年連続で日本一に輝き、
2002年には最高賞にあたる総合部門金賞を受賞、
「富士山麓の高冷地でのおいしい米作りは無理」と言われてきた
長年の固定観念をひっくり返し、
新潟だとかの強豪ブランドと肩を並べた骨太の男。
そして、今年から、海外での米づくりの指導を依頼されて、
海外を飛び回る予定の武藤傳太郎さん、
(はあ、武藤さんの説明長かった!一部みほさんのページから抜粋。)
に話したのです。

(日本一になった武藤さんのお米をたべてみたりしたよ。)
その話を受け、武藤さんは、この鐘山苑の液肥を、
去年、自分のお米づくりで使ってみることにしたのでした。
ついでに、畑でもこれを使って野菜もつくっちゃおうということで、
みずほ村代表のみほさん(私の友人)に声がかかり、
「こんなプロジェクトがはじまるけど、一緒にどう?」と
お誘いを受けたのでした。
そして、そこから、ありがたいことに私にも、
「一緒に畑やんない?富士山のふもとで!」と誘いがあり、
ちょうどタイミングよく、
「自然の中で体を使って働きたい」願望が高まっていた私は、
「やるやる!」と飛びついたのでした。
ふう。一気に書いたぞ。
意味わかったかな?
さて、そして、この武藤さんの去年の米作り、
私たちも田植えを手伝ったこのお米は、
去年の秋にもちろん収穫され、
涙がでるほどおいしいお米になり、
そして、なんと、全国米コンクールで、
「金賞」をいただいたのでした。
〈豆情報〉
この全国米コンクールのことで武藤さんが、
山梨放送(だったかな?)に取材を受けていて、
その放送されたビデオをみたのだけれど、
このコンクール、おもしろかった。
まずは、機械で、お米の成分を調べるの。
でんぷんがどれくらい入ってるかとかね、数字になってでてくる。
でも、それだけじゃ決まらない。
加えて、40人くらいの「審査員」がいて、
小さくお皿に盛ったお米を、真剣な顔で食べ比べて、
「甘さはどれくらいか、ねばりはどうか」とか、
いっぱいあるチェック表をチェックしていくの。
お水で口を整えながら。
この合計点で金賞が決まる。
ああやって、人間の「これはおいしい」で決まるんだね。
ということで、
この液肥がちゃんとしたよい肥料だということが、
去年の米づくりと、野菜づくりによって、
実際の体験としてわかった。
本当においしかったんだ。
お米も野菜も。
うまいんだよね。
あまい。
で、今年からは、畑を、鐘山苑の目の前の空き地に移し、
鐘山苑の料理長高根さんやら市川さんやらなども一緒に、
本格的に畑作りに精を出すことにしたのです。
さて、そうして、この空き地を開墾してゆくのですが、
それは、また次回。
その前に。
ちょっとばかり、この液肥をつくる「機械」について。
この生ごみを、完全有機の液体肥料にする機械は、
「ビーバックス農法」といいます。
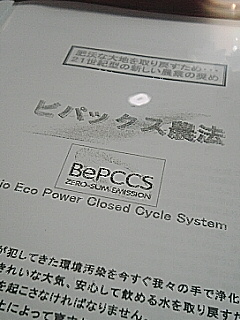
(ビーパックス農法の資料)
この液体肥料の使い方や、
そもそもどういう仕組みで生ごみを液体肥料にするのか、
そして、さらに、なぜこういった取り組みが必要なのか、
ということを、
鐘山苑さんは、この機械をつくった「ビーパックス環境緑化研究所」の所長田中さんをよんで、
液肥を使ってみようかな。と思ってくれた地元の農家の方々のために、
毎月一回、鐘山苑で勉強会を開いています。

(勉強会風景です。)
それに私も参加させてもらってるんだけど、
これが面白くてさ、
興味深々で前のめりできいてしまう。
分子構造とかの話だったり、微生物の話もあったりして、
理系の授業をうけているみたいなんだけど、
「へえええ。そうだったのか!」と、そっち側から見た世の中の仕組みに
いちいち驚いているよ。
素人なうえに、文系の私も、
3回出席して、ようやく意味がわかってきたよ。
(内容はいつもおんなじだけど、先生の気分でちょっとづつ違う。)
それによりますと、結局のところ、
「人間のおなかの中を通すのと同じことをする機械」だということ。
食物を、よい肥料にするためには、
動物に食べてもらって、出してもらうのが、一番。
昔の「たい肥」だね。
やっぱり自然はうまくできているわけです。
で、それに加えてこの機械では、
微生物の力を使ってしっかり発酵させて、
植物に必要な水溶性リンをつくりだしているんだって。
(で、いいのかな?ちょっとあやふや。)
そして、この液体肥料の使い方。
強い酸性だから、濃いと、虫除けにつかえる。
ただ、濃いまま若い葉にかけると、焼けちゃうこともあるから注意。
水で薄めると肥料になる。
土を作るときには、濃いままでよいよ。
栄養たっぷりの土になるから。
ということ。
さてさて、そんじゃあ、次回からやっと、
日誌らしく、開墾からはじめます。
この液肥をつかって、どんな野菜ができるかな。
それでは、また次回!
さんきち
 |
Sankichi Presents [ みずほ村日誌 ]
All rights reserved by Sankichi & SAKRA 2005 |
|
|