![]()
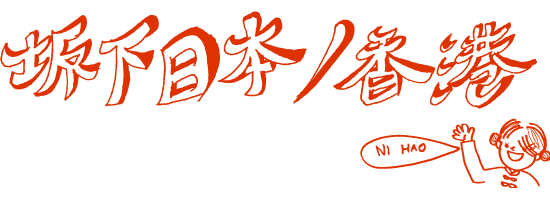
第104回 「勝手にツアーガイド」〜ニホンコンと北京の旅〜」
![]()
ニーハオ、ニホンコンです。
近況はというと、今やっているお仕事の都合で、
毎日自転車で原宿に向かう日々。
片道40分くらいの距離ですが、
これがまた気持ちいいんだー。行き帰りはゴキゲンさん。
平日がここんとこずっと忙しいだけに、
週末の遊び方が半端ない。
このまま溶けて無くなってしまうんじゃないかと思うくらい
力の限り遊んでいる。それはそれで、楽しいが。
さて、今日は。
こんな時には非現実的なことでも考えたくなるものだが、
どうせ妄想するなら実際にやるために、と考えた方が得策、とばかりに
「いかに非現実を現実に変えるか」を考えながら妄想をしてみた。
考えたのは「ニホンコンが案内する北京ツアー」
これは、旅に出たいという気持ちと、
みんな中国を好きになれ!という気持ちと
皆を先導するリーダーになりたいという
いろんな欲求からうまれた企画なのだが、
あながち悪くもないので聞いてください。
4泊5日で行く北京の旅 WITH ニホンコン
1日目:移動日
夕方〜夜到着(多分安い飛行機で行くのでこのくらいの時間かと)

「ニホンコンはイラン航空で北京行き〜」
宿に直行。


この宿ってのがまたニクくて、胡同と言う下町の中にある
「侶松園賓館」という情緒たっぷりの宿。コの字形のホテルに
チャイナチックが詰まったとても静かで素敵なところ。
宿泊はゼッタイココ!と決めている。
しかもタクシーの運ちゃんも分からないくらいの場所なので
ここはニホンコンがいざなわなければ、と思う。
あ、ニホンコンはこないだの一人旅でココの
地下1Fのドミトリー(4人部屋)に泊まりました。
窓がなく朝は日光が入らないのでいつまでも真夜中みたく
同室のみんなで「牢屋」と呼んでましたが。
んで、近所にあるそこらの安レストランにふらりと入り
本場北京家庭料理の洗礼をば。
2日目:天安門〜故宮博物館
中国とニホンコンの朝は早い。
出発は7時。
宿でレンタサイクルをして朝ご飯を食べに街に出掛ける。

もうそんな時間は自転車ラッシュ。10億の人々と自転車と
排気ガスにもまれながらお粥&油条(揚げパン)にありつく。
天安門、故宮博物館を午前中で見学。


ニホンコンとしての狙いはここで「チャイナ!北京!」の
第一関門を通過してもらおうということ。
とりあえずスケールが大きい中国、北京の
その姿を、天安門広場と故宮博物館で味わって欲しいのよ。
しかもステキな毛グッズ(「ケグッズ」ではなく、「マオグッズ」ね)
も沢山あるので毛沢東土産にはもってこいなのだ。
お昼は裏の広東料理屋さん『三大元酒家』で軽く飲茶+広東料理など。
広東料理は中華料理の中でもあっさりしているほうなので
2日目にはよかろうかと。
しかも雰囲気のよい老舗レストランで、胡弓やら琵琶やらを
弾いてくれたりするのだ。そこは。
午後は天安門と故宮博物館が一望できる「景山公園」で
ぐるり360度北京市内を見渡しましょうぞ。
今はもう開発の波でクレーンやら高層ビルやらが建設され
情緒指数が減ってはきているが、それでも情緒はまだあるぞ!
午後は参加者で相談
1、骨董品市場で値切りながら買い物
2、裏道散歩、良さげな家があれば襲撃表敬訪問
3、市内のお寺や公園めぐり(まだまだ山ほどある)

「骨董品市場」

「胡同の小路」
ま、おのおの自由行動だなきっと。
行きたいところに行ってくれ。
困った時の会話は腕とかに書いといてあげます。
んで夕方集合。
夜は王府井市場にある屋台へレッツゴー!
2時間くらい自由行動にして自由に食べ歩いてくださいまし。
昔は見た目も料理も衛生的にヒドすぎて食べる気がしなかったが、
今はとてもきれいになり、観光客も行けるようになった。


「どれを食べるか考えておいてください。
こればっかりじゃないけどさ」
その後は夜茶をしにナイスな茶芸館に行くか
全員で夜の街に繰り出し飲みに行くか
足マッサージでもしてもらいに行くか考えましょう。
うわ。まだ2日目夜だってのに楽しくなってきた。
まだちょっと練りたいところもあり、3、4日目は
来週に持ち越しということで、ヨイ?
取りあえず、私の妄想は限りなく現実に近づけるための
イメージトレーニングみたいなのもです。
行きたい人、この指とまっておいてください。
ツアー参加者は半強制的にニホンコンの中国語講座を
受けてもらうとします。
それでは、下星期二見!
(シャーシンチーアールジェン:来週火曜日会いましょう)
5月24日 坂下日本/香港
追伸;今の時期、まだデモの余韻残る頃かと思います。
ニホンコンはできるだけ沢山の人に北京を好きになって
もらいたいので、あまりイヤな思いをする可能性のある時期、
行動は避けたく、時期をみたいと思います。
| Kaori Sakashita Presents [ サカシタニホンコン ] All rights reserved by Kaori Sakashita & SAKRA 2005 |