![]()
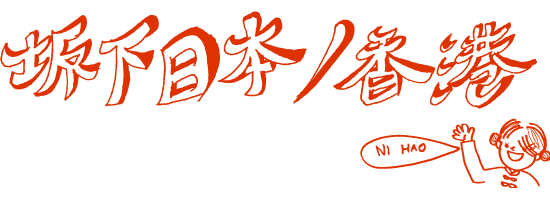
今週末に嫁入りというもので、何ゆえアワアワしてしまいました。
少しお休みがちなのを、お許しくださいマセ。
サカシタニホンコンです。
そうそう、モンゴルのその後の話でしたよね。
思い出していたら、行きたくなってしまいました。
前回の「ものすごい濃ゆい午前中」を経て、午後の予定に移るのですが
これもまたすごい体験でしたわ。
午後のアトラクションは「馬にのる」であった。
ニホンコン、馬なんぞあまり乗ったことがないのですが、
馬夫(マーフー)と呼ばれる馬つかいのおじさんが一緒についてきてくれるので、
安心しながらの馬のりでした。
ただ、この馬夫たちが、タダものではないのだ。
出発しようとしたときに「あの山のてっぺんは見えるかい?」と
聞いてくるのですが、ただの山のテッペンしか見えないので、そう答えたら
「あの山の上に、この馬の彼女がいるんだよ。寂しくて泣いているみたいだ」と。
ふと、思い出したのだが、アフリカとかそんな大自然で生まれ育った人は
視力が4.0くらいあって、向こうーの敵とかが見えるとかなんとか・・
まさに、私の目の前にそんな人たちがいたとは!
もう大興奮で始まった馬のりでありますが、ポッカポッカ歩いては休み、
歩いては休み、といった感じでゆっくりペースで進んでいきました。
途中の水飲み場で腰をおろすと、馬夫さんたち、
さささっとお花を摘んで「ハイッ」とプレゼントしてくれるなど、
自然な姿に涙しそうになったり
で、イキナリ「あ、こいつまだあの彼女のこと考えてるなー」と馬を指して笑ったり。
どうやら、馬の気持ちが分かるみたいなんですね。ホント、感動。
その後、さんざん歩いたり馬に乗ったりしながら、見渡す限り地平線で、
この世に私たちしかいないんじゃないかと思うような瞬間が幾度となくありました。
でも、馬夫さんたち、ちゃんとあるべきところに向かって歩いているんです。
そう、それは私たちが泊まっている「パオ」を目指して戻っているんです。
「どっちが宿か分かる」の問いに、いや、地平線だしなあー、
と思いつつ、同じ質問を返してみると
「今太陽がココでしょ、カゲがこうできるから、家の方向は向こうだよ」と。
ヒ、日時計か〜〜!もう、何から何まで自然で、
ここの魅力に完全にヤラれてしまいました、ニホンコン。
そんな楽しい午後の時間を過ごして、食事の時間が始まりました。
食事の場所は、一番おおきなパオに宿泊客全員が集まり、
そこで大皿料理を頂くのですが、メニューは「昼間と同じ」。
羊の水煮がど、どーん!と出てきて、あとはじゃがいもをいためたり、
野菜炒めだったりなのですが、すべて「ヒツジテイスト」で、
あのニオイに慣れていなかった私には、
ご飯代わりにおいてあるマントウ(白いふっくらパン、ま、いわゆる肉マンの外側)で
おなかを膨らます他なかったり。
で、ここで登場した「キョーレツ」な催しとは。
「モンゴル衣装に身を包んだ現地の方が、馬頭琴などの軽快な音色に合わせてうたい、
踊りながらお客さんにお酒を振る舞うタイム」
が始まったのだ。
かねてから聞いていた、モンゴル族の酒好き宴会好きというのは、
やっぱ「郷に入れば郷に従え」なのかー、と思いながら、
さすがに奴らの好む白酒と呼ばれる蒸留酒(50度)は飲めないので、
これもニコヤカに拒絶!
しかし、奴らはそこで引くような、ヤワなモンゴル族ではないのだ。
どういう手でくるかというと、唄いながら酒をススメるのだが、
こちらが飲まないと分かると、声をあらげて「飲むまでうたう」。
ア〜アア〜 ラ〜ララ〜。どんなウタだったのかは全く覚えていないが、
最後にはもう取って食われてしまいそうな勢いで唄っていた。
くそー。もうこの場は誰かが飲まないと終われない、
と分かったテーブルの一行男子は、こぞってその小さなグラスを飲み干した。
そう、中国でお酒をススメられるというのは、イコール「イッキ」なのだ。
覚えておいて欲しい。
そして、一行は何事もなかったかのように去っていき、
次のテーブルでまた同じ「飲めや飲めや攻撃」をしていくのだった。
「ひゃー、すごかったね、今の」
と、隣を見た私は青ざめた。
そこには、青いを通り越して、真っ白な顔をした男子がいたのだ。
そう、彼は我らと同じグループの日本人男子。
しかも、その子は、お酒が全く飲めないに加え「心臓病持ち」であったのだ。
「な、なんか手足がしびれてきてんだけど・・・」と。
イヤな予感がした。
注:今日は写真は無しなのです。ご了承を。
5月11日 坂下日本/香港
| Kaori Sakashita Presents [ サカシタニホンコン ] All rights reserved by Kaori Sakashita & SAKRA 2004 |