![]()
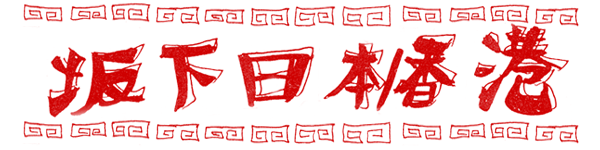
 第30回 転がるニホンコンにコケは生えない
第30回 転がるニホンコンにコケは生えない
富士山噴火やら、日本激震やら、いろいろ巷では騒がれているが
それよりお先に、サカシタニホンコン、2004年、爆発の予感。
来年のニホンコンの予定はこうだ
1月:1ヶ月ほど旅にでる
5月:嫁入り
8月:写真の個展開催!
と、まあ。仕事を辞めてみたり、結婚してみたり、
写真の個展をしたりと忙しい年を迎えるワケなのです。もう、楽しみ、楽しみ。
とはいうものの、先に山口フォトとの写真集を完成させてから、
次のステップに向かわねばなりませんが。
やりたいことは沢山沢山あるのです。
それを来年からひとつひとつやっていこうと思っています。

ま、無理難題ばかりやりたがっているニホンコンではありますが
いつも思うのは「念ずれば叶う」。
この「念」てのが結構デカイんです。
やってやれないことはない、と豪語するニホンコンは、
事実22歳の時に香港に渡り、香港で住みたいという200%の「思い」と
「イキオイ」だけで仕事を見つけ、その場に居着いた経験がある。
それはそれはもうすさまじいもので。
私の気迫も、周りの冷ややかな目も。

もう、人材派遣会社の方からも何度も言われましたよ。
「サカシタさん!頼むから1年日本に帰って下さい!」と。
理由はこうなのだ。
昔流行った香港OL神話なんて終焉を迎えており、
労働ビザがおりるのは、職務経験豊富な語学堪能な女性=優秀な方のみ。
弱冠22歳の小娘なぞがちょっと中国語を勉強したからといって、
香港では通用しないわけなのね。
だから「1年日本に帰る」→「ちょっとでも働く」→
「1年後にまた香港に来る」→「職務経験の欄に何かしら書くことができる」わけだ。
短大卒業→北京留学→香港にてただいま22歳、だと、
ウソつくにも年齢的にムリがあるということなんです。
ただ、「1年たったら気持ちは変わりますよ!
それこそ日本に帰って好きな人なんか出来たら私香港なんて来たくなくなります!」と。
まあニホンコンの読みは外れていないと思う。
日本は楽しいし、友達もいるし、1年暮らしたら、
わざわざ単独で香港なんて行って寂しい思いをしようなぞ、微塵も思わなくなるだろう、と。
私が「カエラナイ」一点張りだと、こうくるのだ
「弱りましたね、サカシタさん。それではあなたの経験(つまり経験無)
と語学力だと、大陸での就職先を薦めます」
大陸とは、香港でなく、中国大陸。
つまり、「リアルチャイナ」なのだ。
「大丈夫です、香港からも近いし、週末には遊びに来れます」
と、いうのだ。人材派遣のオネイサンは。
これはマズイだろ?ゼッタイに。
遊びにこれるからいい、っていうので、すりかえてはならん。
だって、何人も見てきたもん。同じように言われて、中国就職に乗り換えた方を。
そのまま中国の土地にどっぷりつかり、香港なぞは1年に1回しか買い出しに来れない現状を。
「私は香港に遊びにきたいんじゃなくて『住・み・た・い』んです」
ま、人材派遣会社とは決裂したのは、いうまでもない。
無理もない、私が職歴も専門知識もなんも持たず、大陸から押し掛けてきたのだから。

当時5件ほどあった人材派遣会社からほぼ全部ダメ出しを食らわされたニホンコン。
自分で電話帳片手に1件1件電話をかけて、香港に来てから半年後に
「広告代理店」の働き口を見つけました。今思うと、
なぜゆえにそんなにガムシャラだったのかと思うが、自分ゴトながら、
「この人よくやるな」と感心する。
(その半年間の間には、就職先が見つかったものの、
3日で『やっぱビザがおりないから』と解雇されたり、
自分でやばそうと思って辞めたりしたのが何件かありましたが)
その後晴れてその会社でビザがおりたが、弁護士さんに言われた
「『職務経験ナシで労働ビザが取得できた日本人』はサカシタさん、あなたが最後です」と。
思い出すと、私がビザを取得したのが97年。
香港が中国に返還され、外国人の労働規制が丁度かかりはじめた年だった。
事実、その後からの求人情報には必ず「ビザ所有者に限る」が条件となった。
こんな昔の回想話ですが、異国の地でのこの苦労を思えば
これからやろうとしていることは、別にすごい高いハードルでもないと思う。
気合いなのです、気合い。
念ずれば叶う
いつも自分のなりたい自分をイメージしながら、過ごしていきたいと思います。
転がるニホンコンにコケは生えない
「転がる香港に苔は生えない」というフォトエッセイ本があります。
昨日その人の写真集を借りて見たので、ニホンコン風にアレンジし、
こんなタイトルにしてみました。

11月4日 サカシタニホンコン
(ご意見ご感想ファンレターはこちらまで)
| Kaori Sakashita Presents [ サカシタニホンコン ] All rights reserved by Kaori Sakashita & SAKRA 2003 |